-
医療機器洗浄アドバイザーコラム 第51弾
2025年10月21日今回のコラムを担当させて頂きます。中四国エリア担当の川端です。
下手の横好きで休日は家で料理をすることが楽しい。料理をする時によく使うのがフライパン。最近は食材がこびりつかないテフロン加工のフライパンが主流です。
でもそのフライパンも2~3年使っているとだんだん食材がこびりつき始めます。
表面の加工がだんだん摩耗してしまうのがその理由。もうそのフライパンは寿命なので買い替えるしかありません。
でも鉄のフライパンは違います。こびりつかない加工はされていないので扱いは少々難しい。テフロン加工のものに較べると重くて疲れる。洗わずにほっとくとすぐサビてしまう。
でもしっかりメンテナンスしてあげれば食材もくっつかないし一生ものとして長く使える。
いわゆる道具を「育てる」ことで愛着がわき自分だけのものになっていきます。
やっぱりモノを長く使うためには日々の丁寧で愛情を込めたメンテナンスが大切だと感じます。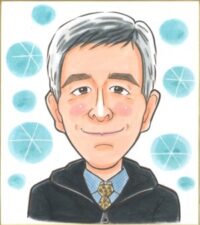
中材業務もこれと共通するものがあるように感じます。清浄度を求めて業務を行うことが
第一命題であることは間違いありません。が、同時に器材がより長く使えるように、より性能を維持できるようにメンテナンスを行うことが同じぐらい大事ではないでしょうか。
手術器材の場合「育てる」とはちょっと違うかもしれませんが、愛情を持って大切にメンテナンスすることが清浄度につながるし、ひいては患者様のためにもなります。
今回のコラムでは器材のメンテナンスについて「器材の再生処理」、いわゆる『赤本』の中から、特に金属の腐食の原因とその対処についてご紹介します。
赤本とは『ヨーロッパにおける医療機器の再生処理ガイドライン』とも言うべきもので非常に参考になる資料です。
金属の腐食といっても様々な種類があります。以下にあげていきます。
★事例①―ぽつぽつ穴の開いた腐食がステンレス鋼の表面に発生し、周囲に赤褐色や多色の腐食斑点が見られる。
これは孔食(Pitting)といい、塩化物(生理食塩水や血液中の塩分など)が乾燥して残留し、不動態皮膜を局所的に破壊することが原因です。
予防策としては、塩化物濃度の低い水を使用し、塩化物を含む液体の残留を最小限に抑えることが必要です。
★事例②―骨パンチのスライド部分に摩擦腐食が発生し、茶色の錆が出た。
これは摩耗摩擦腐食(Wear Friction Corrosion)といいます。鉗子のボックスロックなど
金属の擦れる部分や可動部によく茶色の腐食や錆が発生します。
原因としては、潤滑不足や異物があることで摩擦面が粗くなり、不動態皮膜が破壊されることがあります。
予防策として、パラフィン/ホワイトオイルベースの潤滑剤で摩擦面を保護すること。
器械の機能点検の前に潤滑剤を正確に塗布しましょう。
★事例③―はさみのヒンジ部分に亀裂が発生し、顕微鏡で観察すると粒状の破断面が確認される。
これを応力腐食割れ(Stress Corrosion Cracking)といいます。 強い引張り力がかかる部分に見えないヒビが入る腐食のことです。
これが起こる原因として、器械に過剰な応力のかかる状態で、WDでの洗浄など塩化物を含む環境での高温状態など、腐食しやすい状況にある時におこりやすいです。
予防策としては接合部のある器械は開いた状態で洗浄、ラチェット機構の器械は第一ラチェットでロックして滅菌する。応力を最小限に抑え、塩化物の影響を減らすことが大事です。
★事例④―ステンレス鋼の表面が均一に灰色に変色し、腐食が進行
これを表面腐食(Surface Corrosion)といいます。
原因は長期間の水分や酸性物質への曝露です。
予防策としては水分や凝縮水の長時間の影響を避けることが必要になります。
★事例⑤―ステンレス鋼と真鍮の接触部分で腐食が発生し、錆が広がる。
これは接触腐食(Contact Corrosion)といい、異なる金属の接触による電位差が原因で腐食が進行します。
予防策として、WDセット時などに異なる金属を隣あわせての洗浄を避ける、などが必要です。
★事例⑥―ピンセットの接合部や関節部分で局所的な腐食が進行。
これを隙間腐食(Crevice Corrosion)といい、これが起こる理由として、微細な隙間には金属表面への酸素供給が妨げられ酸素が不足し不動態皮膜が再生できない、また乾燥不足で隙間に水分や塩分が溜まると不動態皮膜が再生できない、ということが挙げられます。
予防策として、隙間を十分に乾燥させ、塩分濃度の低い水を使用する必要があります。
★事例⑦―配管からの錆が洗浄中に器具に付着し、二次的な腐食を引き起こす。
最後が異物錆・付着錆(Extraneous and Film Rust)です。
原因としては、配管や蒸気供給システムからの錆の粒子が移行。他の器具に付着し、二次的な腐食を引き起こします。いわゆる「もらいサビ」ですね。
予防策としてはフィルターを使用して錆の移行を防ぐことなどがあります。
以上の7点が赤本では金属腐食の種類として取り上げられており、原因や予防策などについて記述があります。腐食の実例としての写真も豊富に取り上げられています。

これらの事象を踏まえて器材の再生業務を行う必要がありますが、これらをスタッフ各々が認識し、正しい対処をしていくことは非常にハードルが高いように思います。
できれば自動的に機械的に器材メンテナンスが行えるのが理想的ですよね。
私たちNCCが目指している「ダメージレスの洗浄」を皆様にご提案できることがいくつかあります。それによりそれぞれの現場様にあった『育てる』メンテナンスをご提供できます。例えば、「錆び落としをしても錆びる製品は、不動態化再形成という技術で、錆びにくい医療器材に変化させてく」などの提案もさせて頂けます。
ご興味のある方は是非お問い合わせ下さい。
NCC Column LIST

